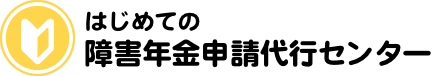障害年金ってどんな年金?
障害年金とはどんな年金かご存知でしょうか?
まず、年金といえば65歳から受給できる老齢年金が一般的によく知られていますが、障害年金はその老齢年金と同じ公的な年金の1つで、65歳前に病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から給付される年金制度です。
ただ残念なことに、障害年金の制度自体はあまり知られていません。2014年の厚生労働省の調べで障害年金の受給者は194万人とされていますが、本来受給できる方はもっと多く、制度を知らずに受給できていないというのが実情です。
また、障害年金制度を知っていても、年金制度のわかりづらさや書類を揃えられないなど、さまざまなハードルがあり受給を断念する方も大勢いらっしゃいます。
当センターでは、障害年金の制度を皆さんに知っていただき、障害年金を確実に、そしてなるべく早く受給していただくためのサポートを行います。



どんな人が受給できるの?
障害年金を受給できる方は、20歳〜64歳までで、日常生活を送るのになんらかの支障がある方です。
その支障とは、うつ病や統合失調症などの精神疾患の方、糖尿病による合併症を起こした方、人工透析を受けている方など、幅広い傷病が対象となっています。
障害年金は、決して重度の障害がある方だけではなく、幅広い方が受給対象となる年金です。
障害年金の受給要件
障害年金の受給には、3つの条件を満たしている必要があります。
- 障害の原因となった病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)を証明できること
- 保険料の納付について、支払わなければいけない期間の3分の2以上納付していること(免除を受けている方、直近1年間納付している方も対象となります)
- 日常生活に支障のある障害状態にあること
対象となる傷病例
障害等級とは?
障害の程度により障害等級認定が行われ、その等級によって障害年金の受給額が変わってきます。

障害等級1級
身体の機能障害や長期の安静を必要とする病気のために、日常の身の周りのことを他人の介助なしではできない程度のものです。

障害等級2級
身体の機能障害や長期の安静を必要とする病気のために、日常生活で著しい制限を受ける場合や制限を加えることを必要とする程度。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて 困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。

障害等級3級
労働が著しい制限を受ける場合や労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受ける場合や労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。
自分も障害年金受給資格があるかも?!
受給対象者かどうかの判定は、ご自分での判断は難しいものです。
受給対象者なのか簡単に判定できる「簡単1分!無料受給判定」のサービスもご利用ください。
また、最初に間違った対応や申請をしてしまうと、年金を受給できなかったり、受給額が減ってしまったりすることがあります。当センターでは、専門のスタッフによる個別無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。